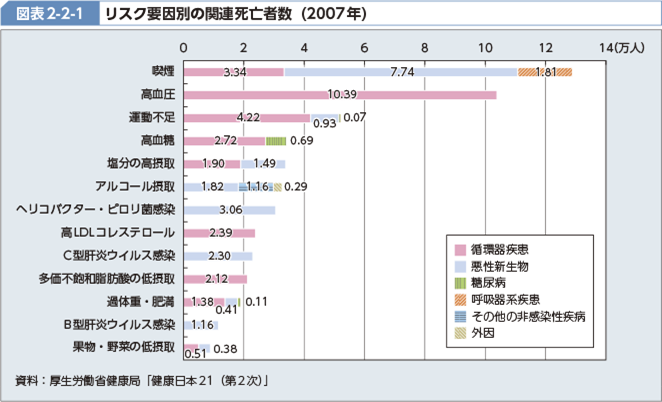「ビタミンCは風邪を治す」との仮説があります。ビタミンCを入れた試験管内で、免疫細胞が活性化していることが、この説の根拠です。
しかし、この論文にあるように、風邪にかかってからビタミンCを摂取しても効果はありません。ビタミンCを毎日1~2g摂取していれば、風邪症状期間を短縮させることは8~13.6%の人にあります。さらに、こちらの論文によると、ビタミンCの毎日1gの定期摂取で、女性は1.25倍~1.97倍白内障になりやすくなります。
「実験室ではこうだったが、人間に摂取させてみたら違った」ことはよくあります。同様に、「動物実験ではこうだったが、人間では違った」こともよくあります。だから、最近認可されている医薬品は全て、ヒトによる臨床試験で効果が認められてから、一般に発売されています。
上の研究から他に言えることは、「水溶性ビタミンはどれだけ摂っても尿として出ていくから害はない」との仮説は誤り、ということです。これも理論上はそうだと思われていたが、実際には違った例でしょう。
なお、「どうしてビタミンCの摂取で白内障になるのか」の答えを正確に答えられる医者は世界中に一人もいません。とはいえ、人間には10万ものタンパク質があり、その相互作用はほぼ全て解明できていないので、ある食物の過剰摂取で予想もしない結果が起こることは、どんな医者でも想像はできるはずです。また、上の研究はビタミンCの摂取と白内障の相関関係を示しただけで、因果関係まで示したわけではない(ビタミンCが白内障の原因とは限らない)ことも、医者なら知っておかなければなりません。
ここから先は私の推測になりますが、摂れば摂るほど健康になる食品や栄養素は存在しないでしょう。厚生労働省が上限を定めていない栄養価は少なくありませんが、まだ科学的に証明されていないだけで、実際には上限値(これ以上摂るべきでない量)が存在すると思います。
 日本で医師の数が約30万人ですから、
日本で医師の数が約30万人ですから、