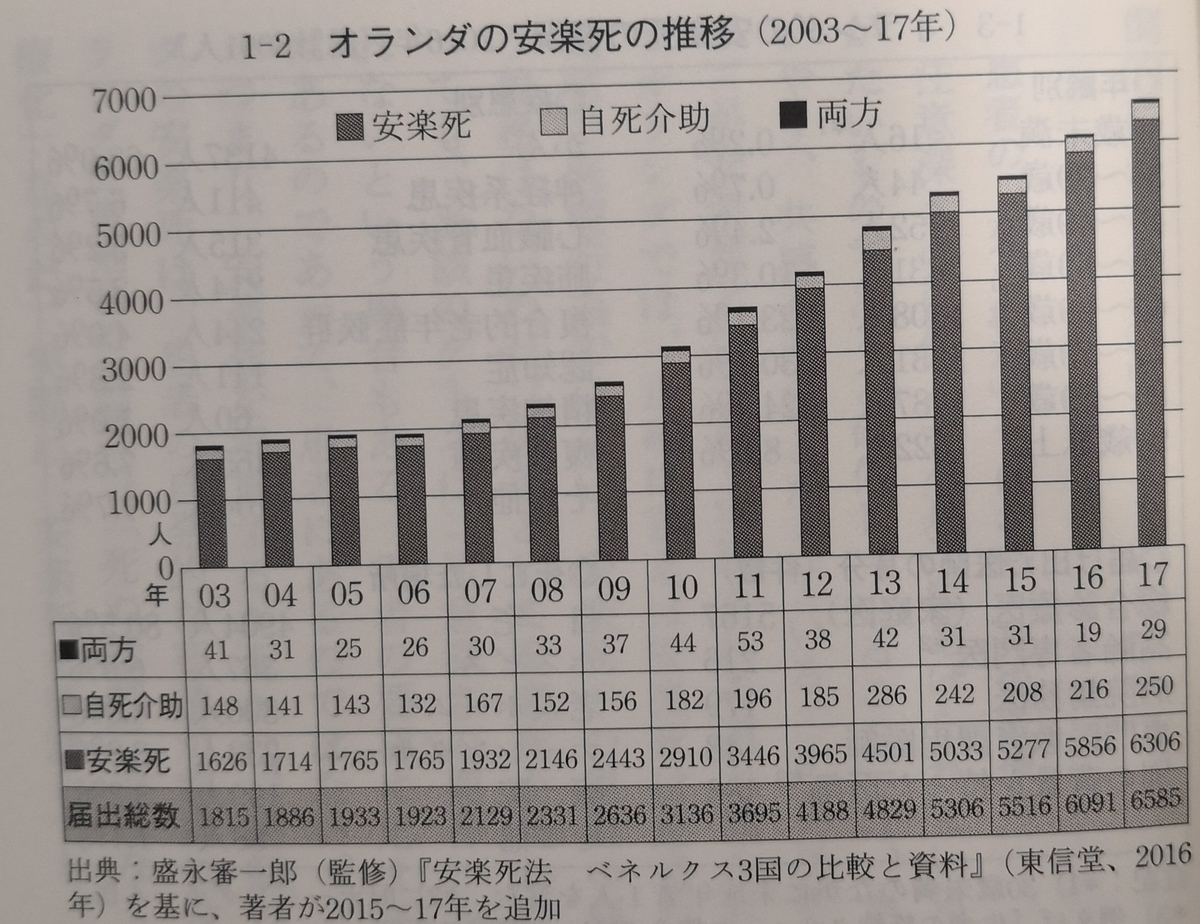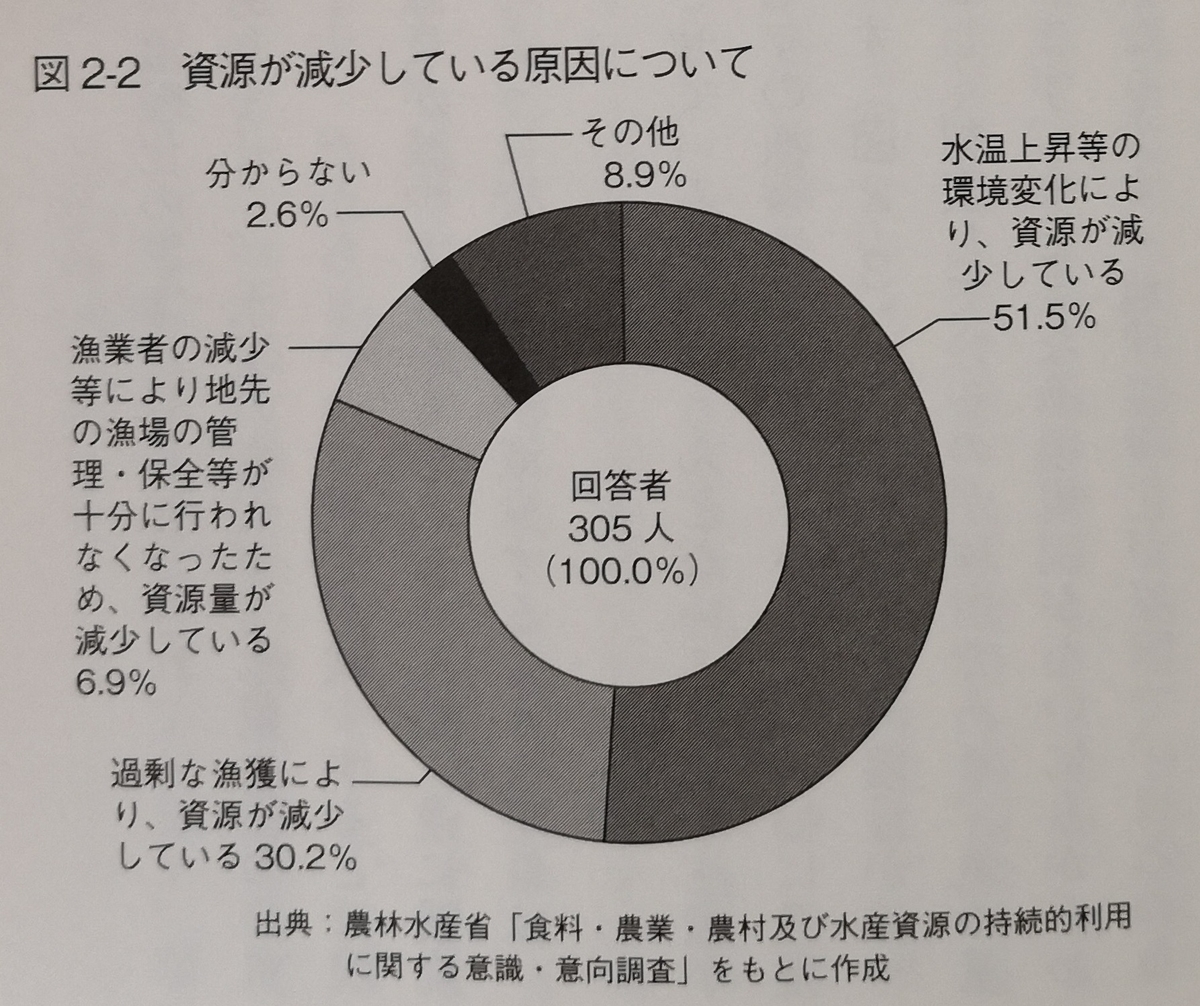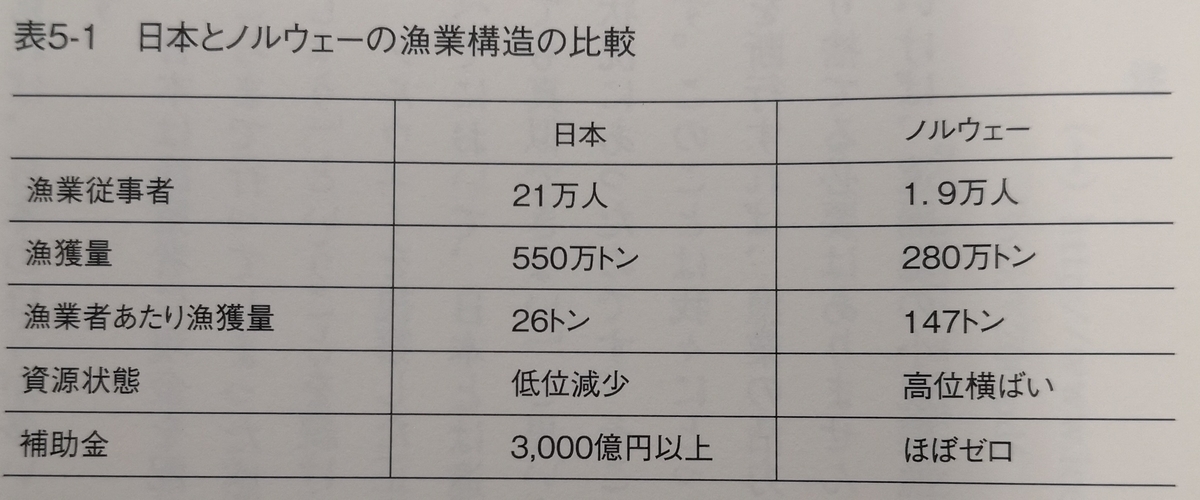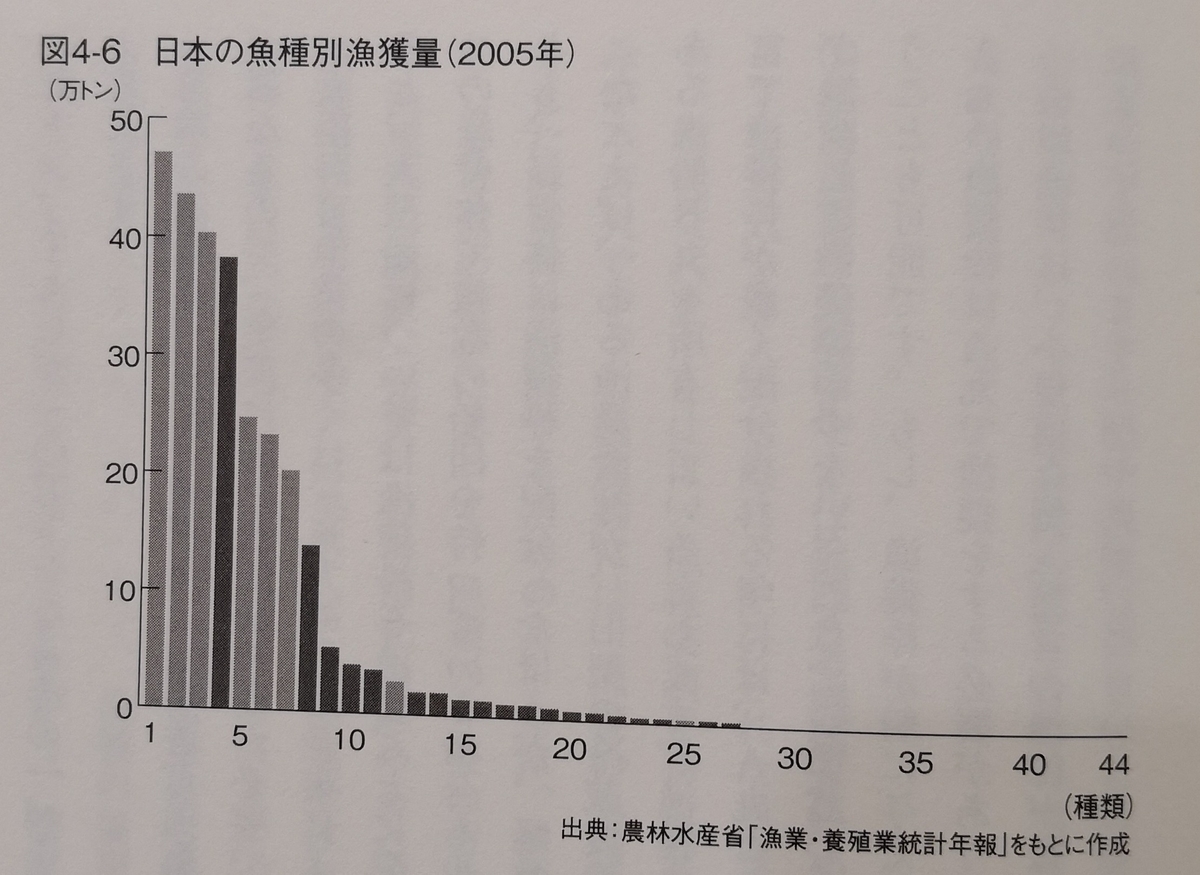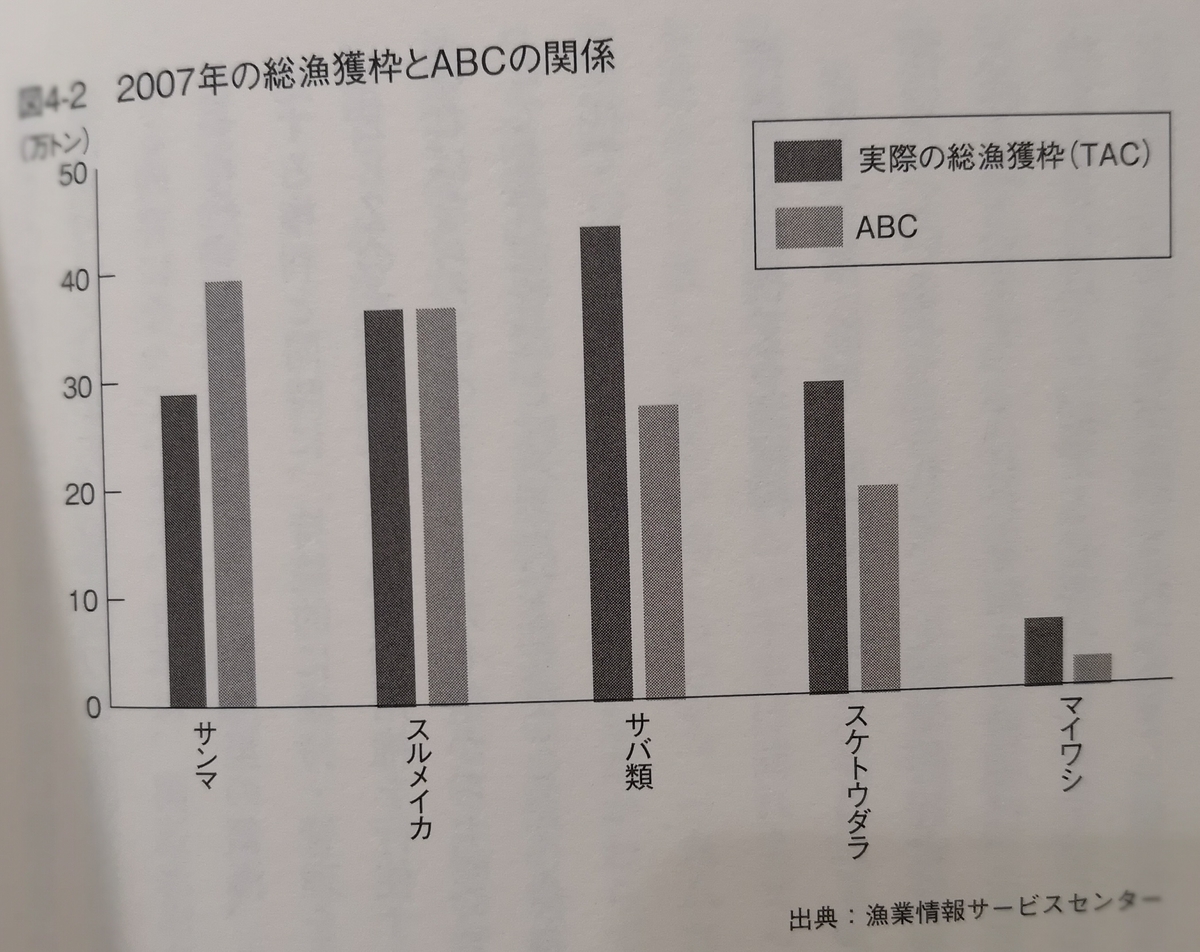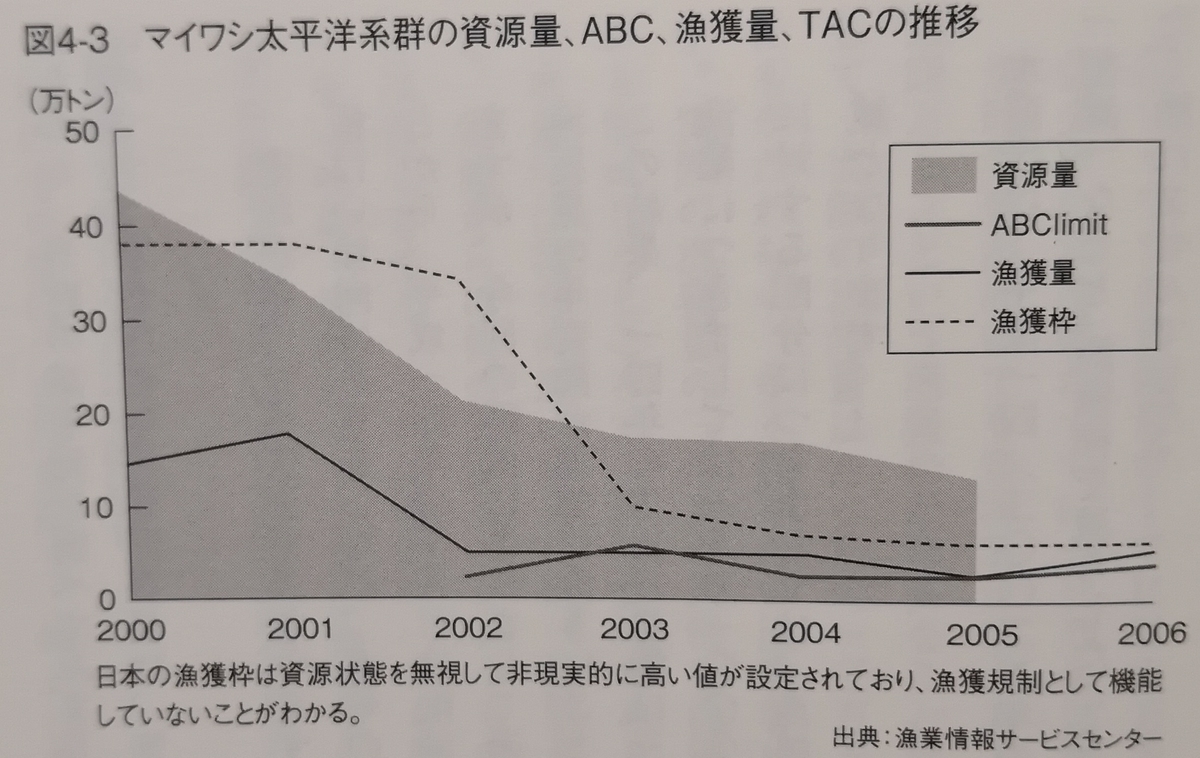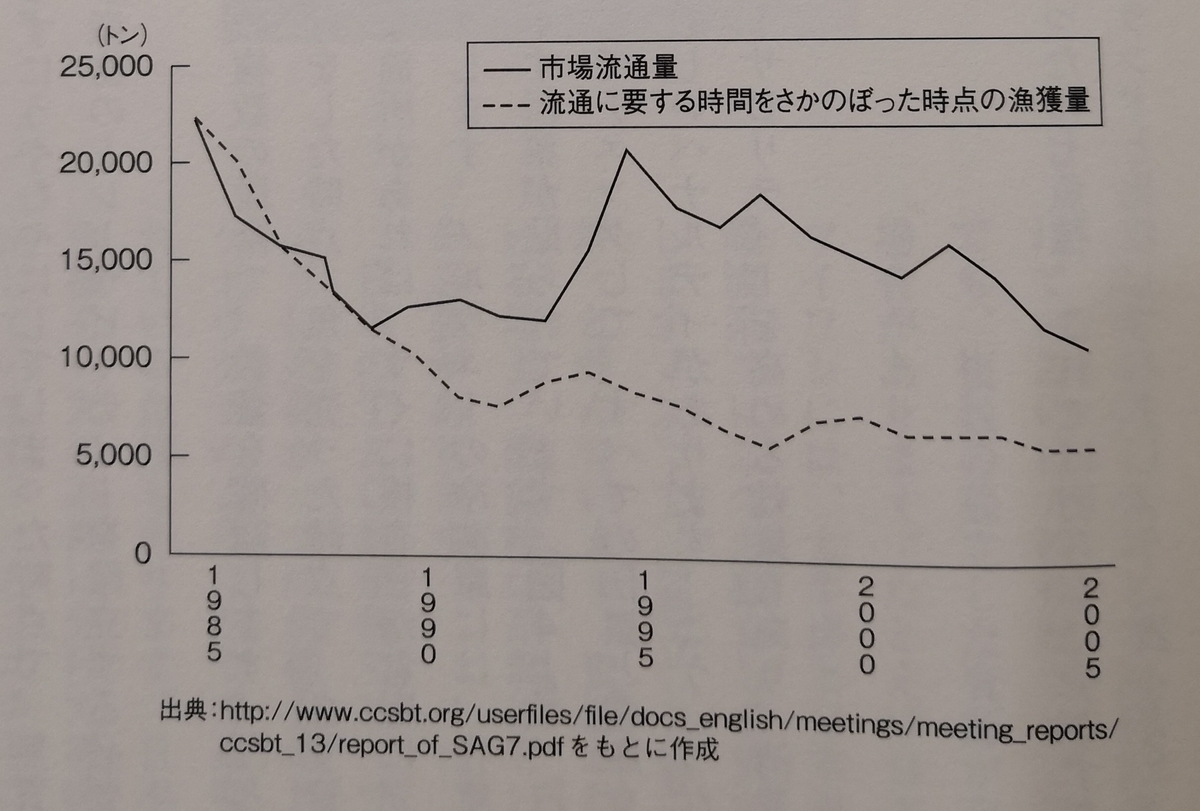前回までの記事の続きです。
カンボジアPKOの75名の日本人文民警察官は、カンボジアもPKOの基礎知識もないまま現地に到着したので、「文民警察官とは何なのか」という疑問に誰もが突き当たることになりました。「現地警察への助言・指導・監視」が公的な目的ですが、それはお題目に過ぎません。「告白」(旗手啓介著、講談社)によると、一部の文民警察官はそのお題目にない仕事をさせられることに怒りを感じています。その代表者が他ならぬ隊長の山崎でした。
カンボジアPKOの一番の目的は、カンボジアに平和をもたらすことであり、カンボジア人だけの力でその達成が難しいからこそ、世界各国の軍人や民間人が来ている、という大前提を日本人文民警察官はあまり認識していなかったようです。
カンボジアPKOの文民警察官の実際の主な任務は、選挙のための有権者登録の支援業務でした。国連ボランティアに付き添って、武器を持たずに警護しながら各地の村や町に赴き、住民たちに「選挙とは何なのか」のビデオを見せたり、有権者登録用の個人カードを作るために顔写真を撮影したりするなど、そうした業務を支援する役割でした。
そもそも「現地警察」といっても名ばかりで、プノンペン政府とそれに対抗する三派が、それぞれが軍とは異なる警察組織を有して、その警察組織同士が反目しあっていました。当然、現地住民もそんな警察たちを信用していません。
大阪府警の文民警察官は以下のような現地警察官の姿を目撃したと記録に残しています。
「カンボジア人の警察官のほとんどは昼間から酒を飲む。密輸容疑のある女性が酔っ払った警察官に声をかけられると、その女性は相手にしないで通り過ぎようとする。すると、警察官は無視されたことに腹を立ててブローニングの自動式拳銃を取り出して、いきなり撃って、射殺する。
ある警察官は密輸などしているはずのない女性に声をかけた。クメール語で、一発やらせろ、と言ったのだと思うけれど、彼をバカにした若い女は無視して通り過ぎようとした。すると、その警察官は背後から拳銃を発射した。若い女はお尻を撃たれ、ズボンを真っ赤にして必死で逃げていった。
これでは誰も現地の警察官を信用しないし、疎ましく思うだけである」
カンボジアPKOの文民警察官は32か国から3500人が集まっていました。しかし、100名以上派遣した14ヶ国のうち先進国は旧宗主国のフランスだけで、それ以外の13ヶ国は発展途上国でした。発展途上国が多くの警察官を派遣した理由は、国連から支給される1日あたり1人145アメリカドルの外貨を獲得できるからです。
日本人文民警察官隊長の山崎は発展途上国の警察官のモラルの低さを次のように嘆いています。
「勤務時間中行方不明になってしまい、どこに行ったか全く分からない者、明らかに遊んでいる者。無線にしても、毎日のように犬、猫、鶏の鳴き声をまねて、仕事の連絡の邪魔をしているバカ者もいる」
UNTACの明石代表と日本人文民警察官隊長の山崎は11月18日にプノンペンで一緒に中華料理を食べています。明石は山崎に次のような苦言を呈します。
「PKOの他の6部門から文民警察部門への批判が強まっている。自分のなすべきことをしていなくて、何事に対しても消極的すぎるというものだ」
こんな批判が来るのは当然だと私は思います。上記のカンボジア警察の横暴を目撃していた、との大阪府警の証言を読んでいた時、こう思わなかったでしょうか。
「そんな違法行為が現行犯で行われているのに、なぜ止めないのか」
現地警察の犯罪行為を止めないだけでなく、国連の文民警察官は一般人の犯罪行為もただ見ているだけです。カンボジアでは「各家にAK47やロケットランチャーがあり、夫婦喧嘩も銃で撃ちあいしたりする状況」なので、犯罪行為なんて嫌でも目に入ります。警察官でなくても、そんな非情な行為を目の前にしたら、止めようとするのに、PKOに来るような「ベストオブベスト」の警察官が止めないのです。ありえません。
明石の批判に対して、「現場を知らない奴がなにを言っているのか」と言わんばかりに山崎は反論します。
「文民警察官には強制捜査の権限を与えられていない。全てを任意で処理しなければならないので、現場ではどこまで自分がやるべきかの判断がつきにくい。クメール語という言葉のハンデもある」
すかさず明石が反論します。
「カンボジアには現在政府がない状態なので、それを代行しているのがUNTACだ。だから、文民警察官の本部長(オランダ人のルース)が強制捜査に必要な令状を発する権限を持っているはずだ」
これを聞いて、「なるほど。そうすれば、強制捜査できるのか」と山崎は考えません。むしろ日本人文民警察官の仕事は「現地警察への助言・指導・監視」に過ぎない、とのお題目にこだわり、強制捜査が現実的でない理由を述べます。
「捜査における人権に関する考え方が必ずしも他国と統一されたものではないことと、文民警察の本部長が令状を発する権限を持つなら、権力のバランス&チェックで疑問があると考えます」
山崎のこの発言に、明石は「そうかなあ」と怪訝な表情になったそうです。この会食の1週間後に、国連の文民警察官がカンボジアの治安維持に責任を負うことはできない理由を、山崎は次のように手紙にしたためて、明石に送っています。
「文民警察官は3500人しかいない。北海道の2倍の国土、大阪と同じ800万の人口を有するカンボジアの治安に直接責任を負うには、明らかにマンパワーが足りない。北海警察は1万数千人、大阪府警は2万人を有している。そもそも、カンボジアの治安維持に文民警察が責任を負うことは、われわれが聞いている職務と大きく異なる」
これに対する明石の反論は載っていませんが、もし私が明石なら、こう反論していたでしょう。
「なにも日本レベルの治安維持など望んでいない。そんなことが今のカンボジアで不可能なことは誰でも知っている。私が嘆いているのは、国連の文民警察官の目前で人が撃たれても見逃されている現状である。そんな現状なら、カンボジア人は国連の文民警察官を信用しないし、国連の他の部署の者たちだって信用しない」
明石が言及した文民警察官の逮捕・勾留権は、1993年2月頃に正式に実現します。これで日本人文民警察官は正々堂々と現行犯で逮捕できるようになったかといえば、そうではありません。山崎が日本政府に判断を仰ぐと、「日本文民警察官が直接・間接に逮捕権の行使にかかわることは、PKO協力法上、不可能である」との回答をしてきたからです。
日本政府の言う通りにすれば、当然、UNTACと齟齬が生じます。山崎はドイツ人の文民警察官参謀長から直接次のように伝えられました。
「事前に日本政府に渡してあるガイドラインに『文民警察官はUNTAC内部の指示命令に従うこと。これに反する自国、あるいは第三者の指示・命令には従ってはならない』と明記されている。もし貴官(山崎)が日本の文民警察官に、日本政府の見解を伝達、指示しているなら、即座に撤回しなければならない。もしも日本政府が憲法であれ国内法であれ、逮捕権の行使を文民警察官に認めていないならば、ニューヨークの国連本部で早急に調整する必要があるだろう」
これがUNTACからの事実上の最後通告だったようです。日本の文民警察官は国連の組織に入った以上、日本政府の指示や命令よりも、国連の命令が優先される国際社会の規則を突き付けられたのです。
山崎としては、国内法に抵触しないように、どうやったら現場で逮捕権を行使できるかを日本政府に考えてほしかったようですが、日本政府は「ダメです」の一点張りでした。だったら、日本の文民警察官はカンボジアから去ればいい、と山崎は考えましたが、それも許されません。
山崎は逮捕権行使の中核となるタスクフォースのリーダーだったのですが、山崎が逮捕権の行使についてゴネるので、リーダーの職をはずされ、副隊長とともに閑職に追いやられます。山崎は「『窓際族』になりました。新しいオフィスに電話はありません! いつ設置されるかも分かりません」と日本人文民警察官たちに手紙で愚痴っています。
これで日本人文民警察官隊長の山崎と副隊長は逮捕権を行使する職務から逃れましたが、他の73名は逮捕権を行使する職務に従事する可能性があるので、なんの解決にもなっていません。山崎は「ばれないようにやってくれ」と日本人文民警察官に言ったそうです。
山崎に言われるまでもなく、AK47を自腹で買って、PKO協力法案に違反した日本人文民警察官はいたことが「告白」には書かれています。ただし、ばれないでやってくれたようで、国会で非難されることはありませんでした。
今回のコロナ騒動でもそうですが、前例のない緊急事態には、上の命令通りにやっていたら、現場はうまく回らなくなりがちです。その時に、上の命令をうまくかわして、融通を利かすことは必要になってくるでしょう。
山崎はUNTACと日本政府の板挟みにあって、平常心をなくすほどイライラしたようです。しかし、私の正直な感想でいえば、単なる警察官ならともかく、東大法学部卒で国家公務員1種合格のキャリア警察官で、しかも日本初のPKO文民警察の隊長に選ばれたほどの逸材なら、「腰が据わらない日本政府の下だと、国連との板挟みになるだろうと思っていた。ここを上手くごまかして、すり抜けることこそ、こちらの腕の見せ所だ」と考えてほしかったです。「ばれないようにやってくれ」も投げやりな言葉としてではなく、「やっぱりこうなったよ。ばれないように、うまくやってくれよ」と笑顔で言ってもらいたかったです。